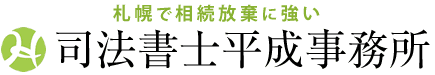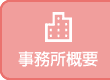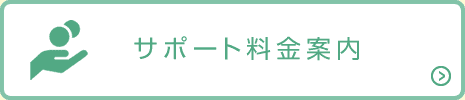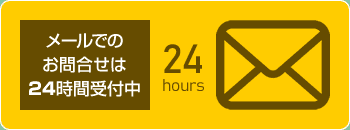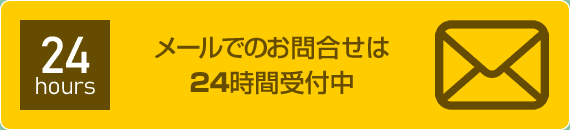札幌で相続放棄の相談・ご依頼を数多く頂戴しております。札幌・札幌近郊で相続放棄をしたい方はお気軽にお問い合わせください。
さて、札幌で相続放棄のご相談を受けていると、「認知症の人の相続放棄はどのようにしたらよいのでしょうか」と聞かれることがありました。ここで認知症の方の相続放棄について解説します。
札幌で相続放棄をお手伝いした際に、「共同相続人のなかに認知症の者がおりますが、相続放棄の依頼はできるでしょうか」と聞かれ、その方にお会いしたことがあります。はじめは「認知症」と聞いていたものの、通常の「老化」の範疇であり、判断能力に問題がありませんでした。このような場合は、普通にご依頼いただいて手続を進めることが可能です。
一方で、これも札幌での事例ですが、こういうこともありました。「認知症の共同相続人も一緒に相続放棄をさせたい」と聞いて、その認知症の方にお会いしたところ、まったく会話が成立しません。もちろん「相続する」ことの意味や、「相続放棄したら、どうなるか」ということについても、理解できているとは到底思えませんでした。このような場合は、普通に相続放棄をしてお終いとはならないのです。
なお、成年後見制度は、本人の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。たとえば札幌市にお住いの方であれば、札幌市営地下鉄西11丁目駅の近くにある「札幌家庭裁判所」がその管轄です。
問題は、相続放棄の期間との関係です。ご承知のように、相続放棄は「相続の開始を知ったときから3か月以内」にしなければいけません。成年後見の手続を進めているうちに、3か月などあっという間に過ぎ去ってしまいます。
伸長の申立てができるのは、「利害関係人」です。誰が利害関係人になるのはケースバイケースですが、家庭裁判所に後見開始の申立を行うのであれば、その申立人が、利害関係人として熟慮期間の伸長の申立ても行うのも手でしょう(そのようなことができるかどうか、事前に家庭裁判所に問い合わせてから行うことをおすすめします)。
このような経験から申し上げると、期間の伸長はだいたい3か月程度が目安となります。本当に特別なケースであれば1年程度の伸長もあるのかもしれませんが、なぜかいつも3か月程度の伸長となっています。
札幌で、相続放棄や相続放棄の熟慮期間の伸長についてお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。相続放棄について、札幌でトップクラスの実績があると自負しています。
さて、札幌で相続放棄のご相談を受けていると、「認知症の人の相続放棄はどのようにしたらよいのでしょうか」と聞かれることがありました。ここで認知症の方の相続放棄について解説します。
そもそも認知症の程度による
「認知症」といえども、その程度は本当にケースバイケースです。札幌で相続放棄をお手伝いした際に、「共同相続人のなかに認知症の者がおりますが、相続放棄の依頼はできるでしょうか」と聞かれ、その方にお会いしたことがあります。はじめは「認知症」と聞いていたものの、通常の「老化」の範疇であり、判断能力に問題がありませんでした。このような場合は、普通にご依頼いただいて手続を進めることが可能です。
一方で、これも札幌での事例ですが、こういうこともありました。「認知症の共同相続人も一緒に相続放棄をさせたい」と聞いて、その認知症の方にお会いしたところ、まったく会話が成立しません。もちろん「相続する」ことの意味や、「相続放棄したら、どうなるか」ということについても、理解できているとは到底思えませんでした。このような場合は、普通に相続放棄をしてお終いとはならないのです。
判断能力が欠いているのであれば、後見制度を利用
判断能力がまったくないと思われる場合は、「成年後見制度」を利用します。成年後見制度は、家庭裁判所に申立てを行い、財産管理人である成年後見人をつけてもらいます。そしてその成年後見人が、成年被後見人(判断能力がまったくないと思われる方)の財産管理を行い、その一環として、相続の放棄をします。なお、成年後見制度は、本人の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。たとえば札幌市にお住いの方であれば、札幌市営地下鉄西11丁目駅の近くにある「札幌家庭裁判所」がその管轄です。
成年後見制度の利用まで、意外と時間がかかる
難しいのは、成年後見の申立てを行っても、すぐにその制度を利用できるわけではない点です。申立てを行うまでも必要書類の収集で時間がかかり、さらには申立て後も家庭裁判所のなかで諸々の手続があるため、成年後見制度を利用すると決めてから2~3か月の時間がかかると思っておいた方がよいでしょう。問題は、相続放棄の期間との関係です。ご承知のように、相続放棄は「相続の開始を知ったときから3か月以内」にしなければいけません。成年後見の手続を進めているうちに、3か月などあっという間に過ぎ去ってしまいます。
期間伸長の申立ても行う
このような場合は、相続放棄するかどうか決める期間(熟慮期間)を伸ばしてもらう手続を利用するとよいでしょう。民法では、次のように定められているのです。民法915条1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
伸長の申立てができるのは、「利害関係人」です。誰が利害関係人になるのはケースバイケースですが、家庭裁判所に後見開始の申立を行うのであれば、その申立人が、利害関係人として熟慮期間の伸長の申立ても行うのも手でしょう(そのようなことができるかどうか、事前に家庭裁判所に問い合わせてから行うことをおすすめします)。
熟慮期間の伸長は、だいたい2~3か月
札幌で相続放棄のご依頼を数多く受けている当事務所でも、熟慮期間の伸長申立はいくつも経験済みです。札幌家庭裁判所の事件もありましたが、札幌家裁以外の他の管轄の申立ても対応したことがございます。このような経験から申し上げると、期間の伸長はだいたい3か月程度が目安となります。本当に特別なケースであれば1年程度の伸長もあるのかもしれませんが、なぜかいつも3か月程度の伸長となっています。
札幌で、相続放棄や相続放棄の熟慮期間の伸長についてお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。相続放棄について、札幌でトップクラスの実績があると自負しています。