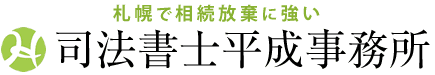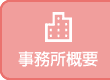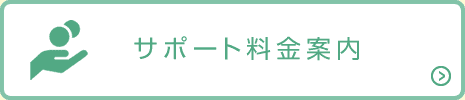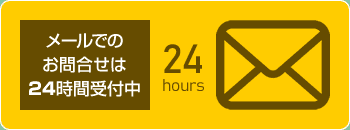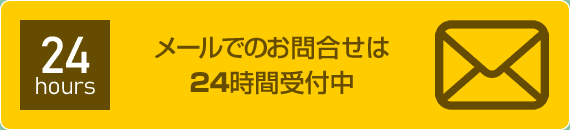民法の条文によると、「一定の事情」があれば、単純承認になります。この「一定の事情」のことを、法定単純承認事由というのです。相続放棄をしたいなら、何が法定単純承認事由に該当するのかを把握し、該当する行為は避ける必要があるのです。
この把握が足りず、相続放棄ができなくなることがあります。
たとえば札幌市に住む相続人のZさんは、相続放棄をするにあたり、遺産の一部を「隠匿」してしまいました。タンス預金などは補足されることはない! 少しくらい貰ってしまっても分からないだろう! このような考えで、遺産の一部をポケットに入れてしまったのです。相続放棄をしたらマイナスの相続財産だけでなく、プラスの相続財産があっても相続できなくなることから、このような行動に出てしまう相続人がいるのです……。
この行為は、法定単純承認事由に該当し、相続放棄ができなくなることにつながります。民法の条文には、次のように規定されているのです。
これは相続人に対する一種の制裁です。相続放棄の効果は「初めから相続人でないことになる」のですから、相続放棄をすると何も相続できなくなります。借金の相続を回避するために相続放棄をするのが一般的ですが、プラスの遺産も相続できなくなるところ、魔がさすことがあるのでしょう。このようなルール違反ともいえる相続人に対しての制裁が、上記条文なのです。
このような理解(上記条文は相続人に対する制裁であるという理解)を前提として、条文には相続放棄の「後」と書かれてありますが、相続放棄の「前」に隠匿等をした場合も、法定単純承認事由にあたるとする見解があります。
したがって、相続放棄をしたいのであれば、相続放棄の「前後」で、隠匿等の行為はしてはいけないと覚えておくとよいでしょう。
隠匿の具体例が知りたいところですが、実際の事例を確認してみましょう。相続人が、被相続人の毛皮等を持ち帰ったことが「隠匿」に当たるとされた事例です。
あなたが相続人であるなら、被相続人のものを持ち去る際は注意をしてください。隠匿に該当すると、相続放棄ができなくなります。
私に(ひそかに)消費するとは、相続財産を処分して原形の価値を失わせることをいいます。
一見すると「私に消費」しているように見えるけれども、正当な事由があるとして「私に消費」にならないこともあります。過去の事例を確認すると、次のように扱われたことがあるのです。
夜具布団を処分することは通常の行為であり、この事例のなかでは特に問題にならないと扱われたのでしょう。
しかしながら、これは「限定承認」の場面の話であって、相続放棄の場面の話ではありません。財産目録を作成するのは、限定承認のときだからです。裁判所で問題になった過去の事例(大判昭和15年1月13日民集19巻1頁)も、同様に述べています。
この把握が足りず、相続放棄ができなくなることがあります。
たとえば札幌市に住む相続人のZさんは、相続放棄をするにあたり、遺産の一部を「隠匿」してしまいました。タンス預金などは補足されることはない! 少しくらい貰ってしまっても分からないだろう! このような考えで、遺産の一部をポケットに入れてしまったのです。相続放棄をしたらマイナスの相続財産だけでなく、プラスの相続財産があっても相続できなくなることから、このような行動に出てしまう相続人がいるのです……。
この行為は、法定単純承認事由に該当し、相続放棄ができなくなることにつながります。民法の条文には、次のように規定されているのです。
(法定単純承認)
民法第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。~以下、省略~
民法第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。~以下、省略~
相続放棄の「後」だけでなく、「前」でも注意
上記条文を読むと、限定承認と相続放棄の場面についての規定ですが、「限定承認」は当サイトの目的から離れますから、限定承認の場面についての説明は割愛します。すると、上記条文は「相続放棄をした後に、相続財産を隠匿し、私に(ひそかに)これを消費」した場合は、相続放棄ができないと読むことができます。これは相続人に対する一種の制裁です。相続放棄の効果は「初めから相続人でないことになる」のですから、相続放棄をすると何も相続できなくなります。借金の相続を回避するために相続放棄をするのが一般的ですが、プラスの遺産も相続できなくなるところ、魔がさすことがあるのでしょう。このようなルール違反ともいえる相続人に対しての制裁が、上記条文なのです。
このような理解(上記条文は相続人に対する制裁であるという理解)を前提として、条文には相続放棄の「後」と書かれてありますが、相続放棄の「前」に隠匿等をした場合も、法定単純承認事由にあたるとする見解があります。
したがって、相続放棄をしたいのであれば、相続放棄の「前後」で、隠匿等の行為はしてはいけないと覚えておくとよいでしょう。
「相続財産の隠匿」とは何か?
裁判所のある見解によると、隠匿とは「相続人が被相続人の債権者等にとって相続財産の全部又は一部について、その所在を不明にする行為」であるとされています(下記の事例について述べられた見解)。財産を隠してしまうと、被相続人の債権者が困ってしまうため、債権者保護のための規定ともいえます。隠匿の具体例が知りたいところですが、実際の事例を確認してみましょう。相続人が、被相続人の毛皮等を持ち帰ったことが「隠匿」に当たるとされた事例です。
■東京地判平成12年3月21日家月53巻9号45頁
相続人が2度にわたって持ち帰った遺品のなかには、新品同様の洋服や3着の毛皮が含まれており、当該洋服は相当な量であったのであるから、~中略~、持ち帰った遺品は、一定の財産的価値を有していたと認めることができる。そして、相続人は、遺品のほとんどすべてを持ち帰っているのであるから、被相続人の債権者等に対し相続財産の所在を不明にしているもの、すなわち相続財産の隠匿に当たる~以下、省略~
相続人が2度にわたって持ち帰った遺品のなかには、新品同様の洋服や3着の毛皮が含まれており、当該洋服は相当な量であったのであるから、~中略~、持ち帰った遺品は、一定の財産的価値を有していたと認めることができる。そして、相続人は、遺品のほとんどすべてを持ち帰っているのであるから、被相続人の債権者等に対し相続財産の所在を不明にしているもの、すなわち相続財産の隠匿に当たる~以下、省略~
あなたが相続人であるなら、被相続人のものを持ち去る際は注意をしてください。隠匿に該当すると、相続放棄ができなくなります。
「私に消費」とは、どんな行為なのか
次に、相続放棄の「前後」でするべきではないのが「私に消費」です。これも法定単純承認事由ですので注意をしてください。私に(ひそかに)消費するとは、相続財産を処分して原形の価値を失わせることをいいます。
一見すると「私に消費」しているように見えるけれども、正当な事由があるとして「私に消費」にならないこともあります。過去の事例を確認すると、次のように扱われたことがあるのです。
■東京控判大正11年11月24日評論11巻民1220頁
被相続人Aの使用する夜具布団は、これを他に施与・焼棄しても、私に消費にはならない
被相続人Aの使用する夜具布団は、これを他に施与・焼棄しても、私に消費にはならない
夜具布団を処分することは通常の行為であり、この事例のなかでは特に問題にならないと扱われたのでしょう。
「悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかった」は限定承認時
上記条文(民法第921条3号)によると、「悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかった」ことも、法定単純承認事由に該当し、相続放棄ができなくなるように読めます。しかしながら、これは「限定承認」の場面の話であって、相続放棄の場面の話ではありません。財産目録を作成するのは、限定承認のときだからです。裁判所で問題になった過去の事例(大判昭和15年1月13日民集19巻1頁)も、同様に述べています。